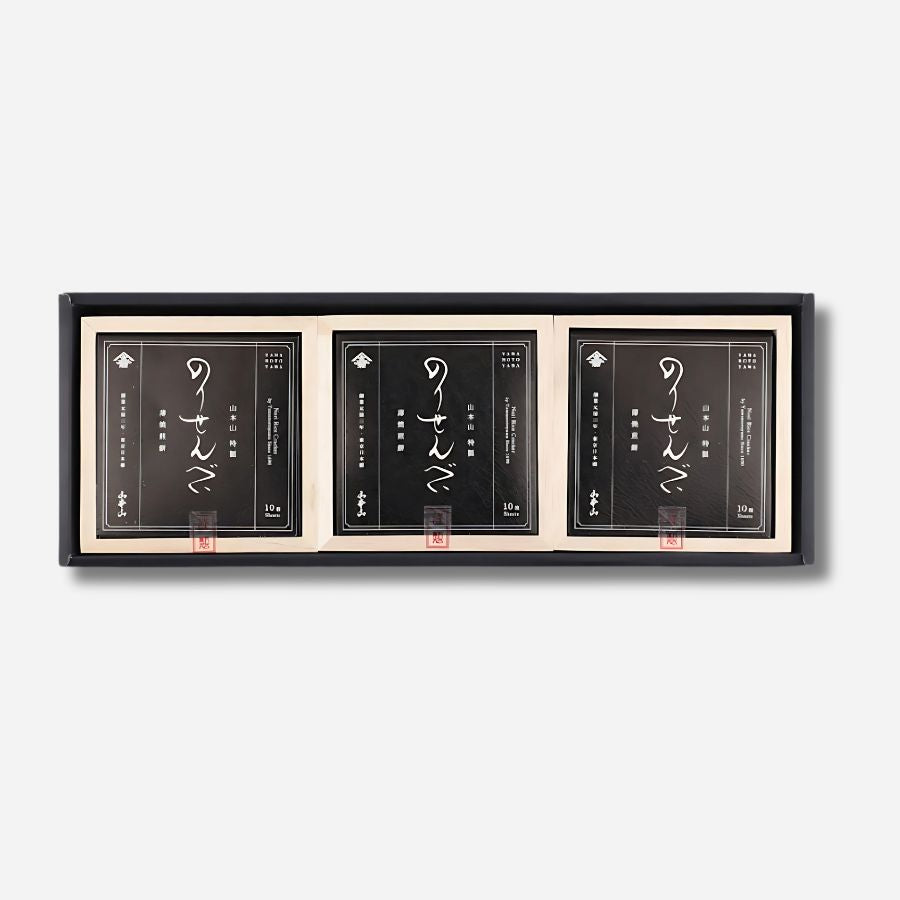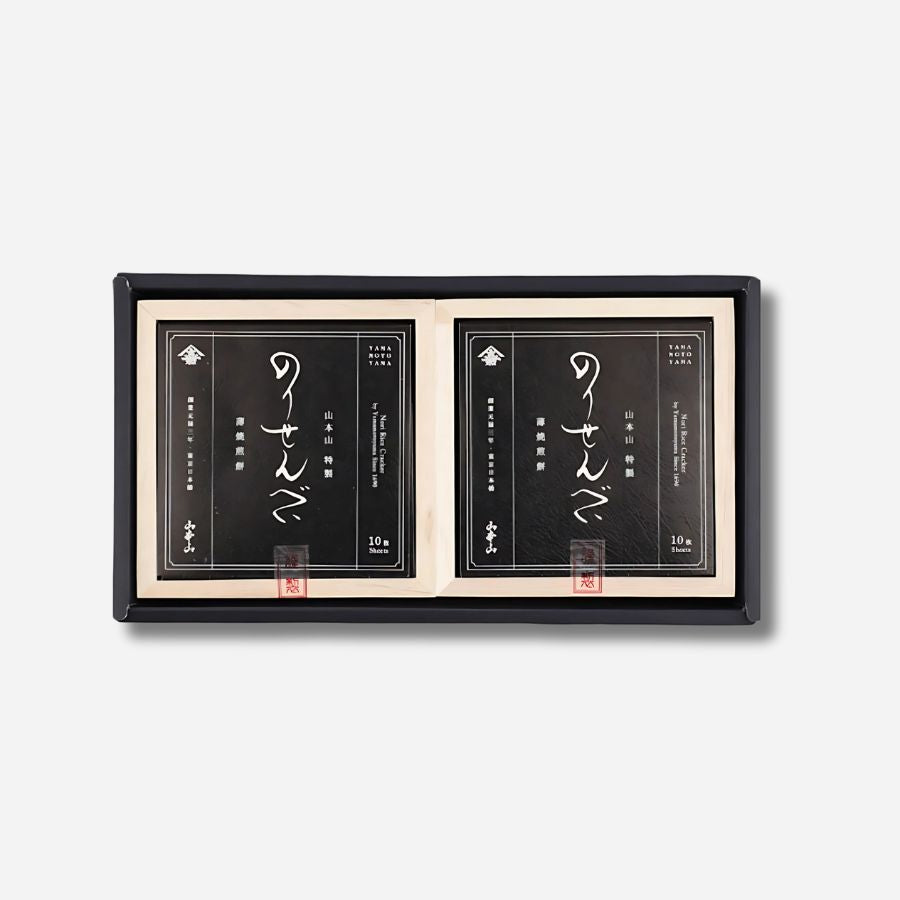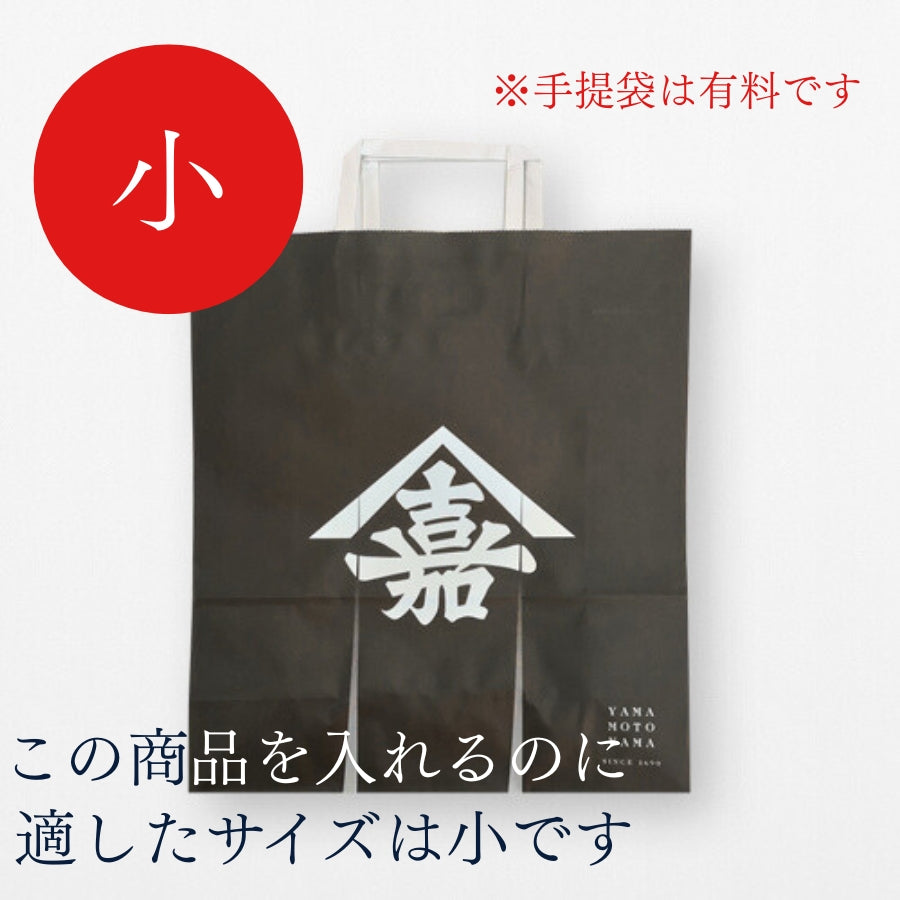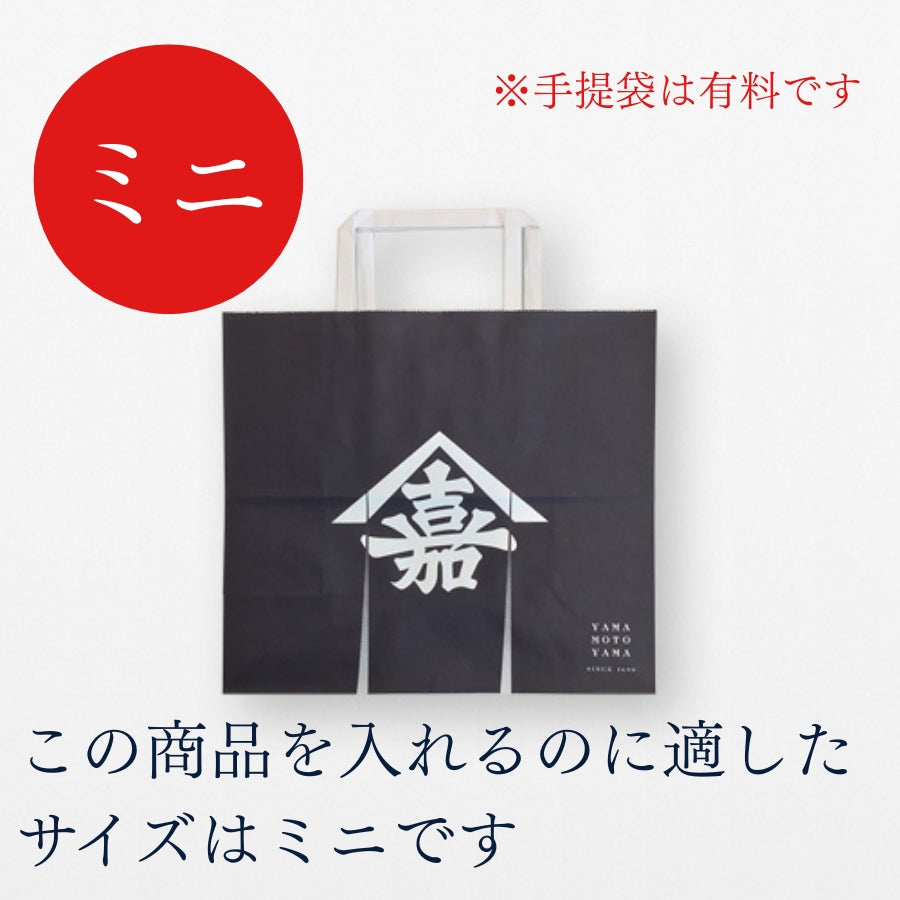お盆は仏教行事じゃなかった?意外なルーツと本当の意味
はじめに
お盆と聞けば、「帰省ラッシュ」に代表されるように、家族や親戚が一堂に会し、ご先祖様のお墓参りをするのが当たり前だと多くの人が考えているでしょう。
迎え火から始まり、盆踊り、送り火、精霊流し、そして今は見られなくなった「藪入り」など、お盆の期間中には多彩な行事が行われます。
しかし、この「お盆」のルーツを辿ると、意外な事実が見えてきます。

お盆は元々、仏教行事ではなかった?
実は、日本古来の信仰では、一年を「正月」と「盆」の二つの時期に分け、それぞれを大切な節目と考えていました。
この時期に先祖の霊を迎え、家族の健康と生活の繁栄を祈るため、人々は旧暦7月15日の十五夜に、一族で集まって収穫物を捧げる「先祖祭り」を行っていたのです。
現在のお盆は、この古来からの先祖祭りという習俗に、仏教行事の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が合わさったものだとされています。

飢えを救う「盂蘭盆会(うらぼんえ)」の教え
この盂蘭盆会(うらぼんえ)とは、飢えに苦しむ先祖を供養するための仏教行事です。
お釈迦様の弟子のひとり、目連(もくれん)が、地獄に落ちた母を飢えと渇きの苦しみから救うため、お釈迦様の指示により7月15日に供養を行ったという故事にちなんでいます。
当初は亡くなった先祖の供養が主だった盂蘭盆会(うらぼんえ)の習俗も、インドから中国に伝わる過程で儒教の影響を受け、先祖だけでなく、存命中の両親の供養にまでその対象が拡大されました。

そして日本に伝えられると、さらに独特の発展を遂げます。
そこから、先祖を敬うだけでなく、一年間不幸がなく、両親が健在な家では、その両親の長寿と健康を祝う「めでたい盆」という行事が生まれました。
これは「生身玉(いきみたま)」や「生盆(いきぼん)」などとも呼ばれ、子どもたちが親元へ食べ物を持参し、親子で霊魂の力を強めようとするものでした。やがて、この習慣がお中元の習俗へと結びついていったと考えられています。

二つの伝統が結びついた「お盆」
このように、同じ時期に行われていた古来の先祖祭りと、仏教行事の盂蘭盆会(うらぼんえ)は、いつしか結びつき、次第に仏教色の濃い行事として日本中に広まっていきました。
本来の意味を考えると、お盆に故郷へ帰るということは、単にお墓参りのためだけではないのです。
そこには、ご先祖様への感謝と共に、今生きている家族、特に親の健康や長寿を願い、共に喜びを分かち合うという、より深く温かい意味が込められています。
かくいう私も犬や仕事を理由にもう十年以上お盆に帰省などしていないのですよね…。まだ元気でいてくれる両親の顔を見に、今年は犬二匹を連れて帰省してみようと思っています。