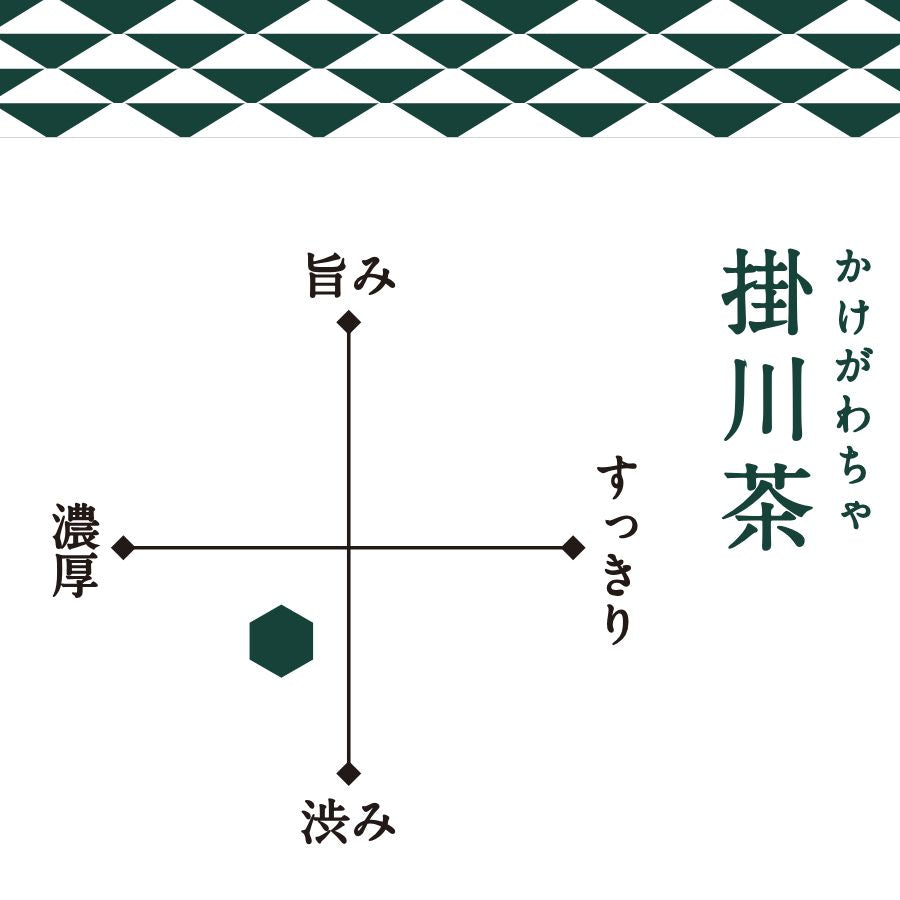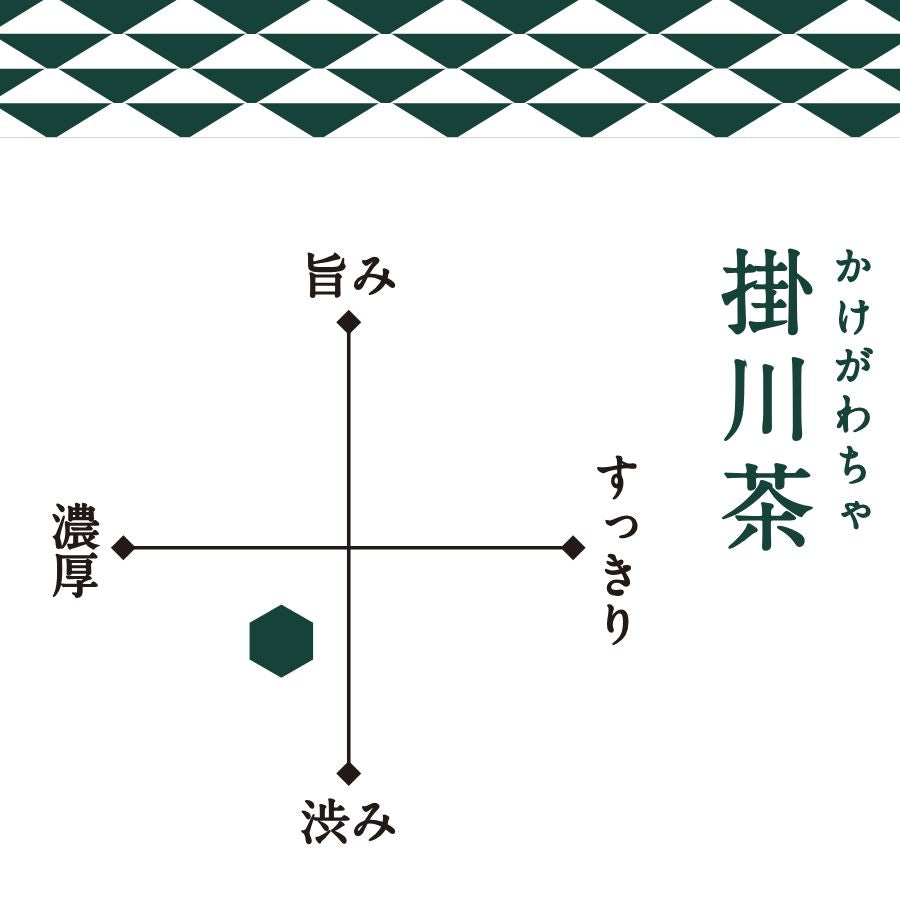静岡、お茶の産地を訪ねて ━ 萌え立つ新緑、熟練の技 - 静岡茶摘み密着ルポ
はじめに
新茶の香りが満ちる5月。
私は、静岡県の広大な茶園を訪れ、一年で最も活気づく茶摘みの現場に密着しました。
輝く緑と、茶葉の生命力に満ちた香りに包まれ、いよいよ始まる収穫の瞬間。この特別な体験を、皆様にご紹介します。

朝の茶畑、収穫が始まる
朝露がまだ残る午前7時50分、摘採機が唸りを上げ、鮮やかな緑の絨毯を滑るように進んでいきます。
早朝からの作業ですが、茶農家の方によると、単に朝早ければ良いというものではないとのこと。
茶葉に露がついていると蒸しが均一にならないため、最適なタイミングを見計らって摘み始めるそうです。
この日の摘み取り作業は、2台の乗用摘採機を操る2名の作業員と、収穫された茶葉を運ぶ2~3名のトラック担当者を中心とした、総勢5名体制で行われていました。
茶畑の畝に沿って、乗用摘採機は高さがミリ単位で細かく調整され、最も柔らかな新芽だけが丁寧に収穫されていきます。
新鮮さを追求!摘採から加工場への迅速な輸送
摘み取られたばかりの茶葉は、まだ呼吸をしており、時間の経過とともにどんどん鮮度が落ちてしまいます。
そのため、できるだけ早く荒茶工場へ運ばなければなりません。
収穫された茶葉は30分以内に速やかに集められ、その後、1時間から1時間半という短時間で、三トントラックに積まれ加工場へと運ばれていきます。

特に、この時期の一番茶は、収穫直後から熱を持ちやすいため、トラックへの積載量を少なめに調整するなど、茶葉の品質を損なわないよう細心の注意が払われます。
搬送用のトラックには、専用のファンが取り付けられており、庫内に熱がこもるのを防ぎ、茶葉が最高の状態で工場に到着するよう、徹底した管理が行われていました。
このようにして運ばれた茶葉は、その日のうちに加工処理が開始されます。

摘採の準備:時間との勝負と人々の連携
茶摘みの時期は、茶葉の生育状況を細かく見極め、直前に決定されます。
かつてはこの時期になると、茶農家の方々は茶園付近に約1カ月もの間泊まり込み、茶葉のわずかな変化も見逃さず、いつでも摘採に入れるよう待機していたそうです。

この日の夕暮れ時から夜にかけては、翌日に控えた「かぶせ茶」の茶摘みに向けた重要な準備作業、被覆を剥がす作業が行われました。
広大な茶畑一面に広がる黒いシートが、翌日の陽光を浴びるために手際よく剥がされていきます。これは、新芽を十分に成長させ、摘採に最適な状態にするための欠かせない工程です。
この大がかりな作業には、近隣の農家の方々だけでなく、この時期ならではのアルバイトの方々も応援に駆けつけます。総勢10名ほどの体制で、一人あたり1.5ヘクタールもの広大な面積をカバーするというのですから、その連携と体力には目を見張るものがありました。
この時期の茶園は、早朝から日が沈むまで、まさに一年で最も忙しく、多くの人々が情熱を注ぎ込む、活気に満ちた時期なのです。

茶葉の品質を支える一年 - 静岡の茶園管理
美味しい茶葉を育む上で最も重要なのは、新芽が芽吹く収穫期だけではありません。
実は、前年の夏から秋にかけて成長する「親葉」の丁寧な管理が、その年の新茶の品質を左右する鍵となります。

繊細なチャノキは、日本の厳しい自然環境の影響を受けやすく、特に寒さと暑さには弱い性質を持っています。そのため、茶農家は一年を通して、様々な工夫を凝らして茶畑を守り育てています。
冬の厳しい寒さから茶葉を守る上で、特に重要な役割を果たすのが防霜ファンです。
気温が氷点下に近づき、茶葉に霜が降りて品質を損なう恐れがある際には、この巨大な扇風機が稼働します。
上空の比較的暖かい空気を地表に送り込むことで、茶畑全体の温度をわずかに上昇させ、霜の発生を抑制する効果を発揮します。

一方、連日のように日照りが続く真夏は、強い紫外線によって茶葉が焼けてしまうのを防ぐための対策が不可欠です。
そのため、茶園では定期的な散水が行われます。葉の表面を冷やすだけでなく、適度な水分を与えることで、茶樹の活力を維持し、品質の低下を防ぎます。
近年では、より効率的で環境に優しい水管理を目指し、点滴灌水システムを導入する茶園が増えているそう。
これは、根元に細いホースを張り巡らせ、必要な量の水をゆっくりと、かつピンポイントで供給する仕組みです。
過剰な水分による茶畑の蒸れを防ぎながら、茶樹の根にしっかりと水分を届けることができるため、高品質な茶葉の育成に貢献しています。
茶樹の寿命と育成サイクル:品質を支える剪定の技
チャノキは、およそ30年が経済的な寿命とされる作物です。
新しく植えられた苗が初めて収穫できるようになるまでには3年を要します。
その後、茶樹は年に約10cmずつ成長を続けますが、その活力を保ち、安定した収穫量を確保するためには、3~4年ごとの剪定が欠かせません。
こうすることにより、お茶の樹の若返りを図ることができ、樹勢がさらに増し、お茶の味わいも一層深まるのです。
特に、最も重要な一番茶の収穫が終わる5月中旬頃に剪定を行うことで、茶樹は新しい枝を力強く伸ばし、翌春には再び良質な茶葉を実らせるサイクルが確立されます。
摘採サイクルと茶葉の多様な活用
静岡の茶農家は、茶葉の品質と最終的な用途を見据え、摘採のサイクルを細やかに管理しています。
春に最初に摘み取られる一番茶は、その年の最も上質な茶葉として新茶や上級煎茶として珍重されます。
それに続く二番茶、三番茶は、一番茶とは異なる風味を持ち、それぞれが持つ個性が活かされます。
また、樹高が高くなりすぎた茶樹は、効率的な管理のために「台切り」という大胆な剪定が施され、お茶の木を半分くらい刈り込みます。
台切りから約一ヶ月後には、再び勢いよく緑の新芽が萌え出します。これらの新芽は、主にペットボトル飲料やほうじ茶といった加工品に利用され、その特性が最大限に活かされているのです。

まとめ
茶農家の方々にとって、この新茶の時期は、一年間、丹精込めて育て上げた茶葉がようやく製品として形になる、まさに実りの秋です。
同時に、この収穫期は、翌年の豊かな茶葉の生育を左右する、極めて重要な準備期間でもあります。茶摘みから加工まで、時間との闘いの中で行われるすべての作業が、未来の品質を左右するのです。
取材中、畑一面に広がる息をのむような鮮やかな緑と、茶摘みを行う人々の活気ある声に包まれ、私は静岡のお茶産業が持つ生命力と、その確かな未来を肌で感じました。