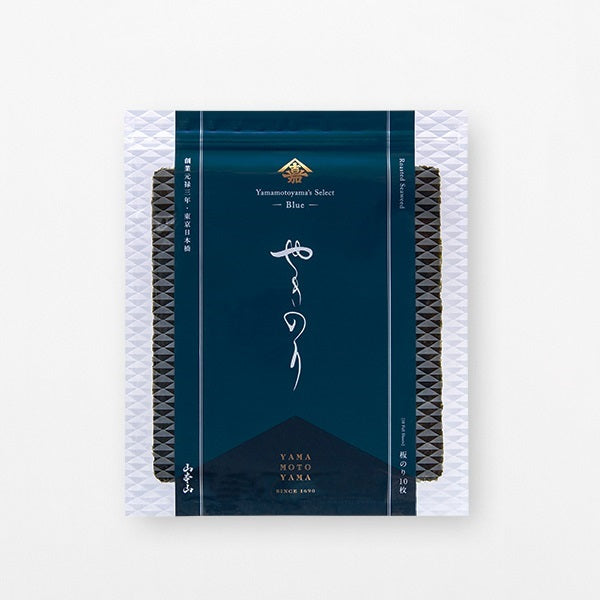【プロ直伝】おにぎりの基本!丸・三角・俵・太鼓、4つの形の握り方とコツ
はじめに
おにぎりには大きく分けて、4つの形があります。三角形、丸形、俵形、太鼓形です。
三角形や丸形はご飯の中に具材を入れやすいのが特徴で、太鼓形は混ぜ込むのに最適。俵型は具材を入れないスタイルも珍しくありません。
同じ具材でも、形を変えるだけで、新しい発見があるかも。ぜひ、色々な形に挑戦して、おにぎりの世界を広げてみてくださいね!

おにぎりの4つの形と握り方
1. 三角形
いまではおにぎりの主流であり、最もスタンダードな形。
江戸時代に、今の神奈川県にあった川崎宿で作られ始めたのが起源といわれています。握りやすく、食べやすい三角形のおにぎりは、持ち運びに便利で食べやすい、旅人の携帯食でした。
古くは山形に握った頂点に紙が宿ると信じられ、三角形になったという説もあります。
握り方
- おにぎりを握るとき、まず左の手のひらにご飯を乗せます。
- 次に、右手を山のようにしてご飯を上から優しく押さえ、三角形の角を作ります。
- この形を崩さないように、手前に数回転がし、きれいな三角形に整えましょう。

2. 俵形
横に細長い俵型の形状は、関西圏ではなじみの顔。「幕の内弁当」や「駅弁」でおなじみのスタイルです。
一説によると、関西地方で好まれる味付け海苔がくるりと巻きやすい形だからという説もあります。
上下をもってくるくると回しながら握るのがコツです。ちなみに、九州は関西文化の影響を受けているので、俵型の地域も多いようです。
握り方
- まず、左の手のひらに、炊きたてのご飯をふんわりと乗せます。
- 次に、おにぎりの両サイドを平らになるよう、右手の親指で片側を、残りの指で反対側を、それぞれ軽く押さえます。
- 右手の指でご飯の上下を持ったまま、左の手のひらの上で優しく転がします。
- 形が整ったら、おにぎりの完成です!

太鼓形(円盤型)
球状ではなく、側面がつぶれているのが特徴。
太鼓形は東北で多い形ですが、最近はコンビニで売られている赤飯やチャーハンを使ったおにぎりにも太鼓形が用いられています。
葉っぱで巻いたおにぎりや焼きおにぎりに太鼓型(円盤型)が多いのは、包みやすく焼きやすい形状だからでしょう。
握り方
- 左の手のひらにご飯を乗せます。
- 右手をふんわりとドーム状にして、ご飯の側面に優しくかぶせます。
- 左手の親指でご飯の真ん中をそっと押さえつつ、右手を動かします
- ご飯をくるくると反時計回りに回転させましょう。
- 少し平たい丸い形に整えたら、はい、出来上がり!

丸形
ご飯を球状にまとめたもの。
江戸時代に三角おにぎりが登場するまではこの形がスタンダードでした。もっとも原始的なおにぎりの形といえます。
現在は九州でこの形が多いといわれています。丸まるおにぎりは、あまり大きく握らず、一口大の食べやすいサイズが特徴的。手のひらで丸く転がすようにして握りましょう。
握り方
- 左の手のひらにご飯を乗せます
- 右の手はふんわりとドーム型を作り、ご飯を包み込むようにして添えます。
- 両手を動かし、ご飯を優しくコロコロと転がしながら握ります。
- 全体が丸くまとまるように整えたら完成です。
※上記は、右手を利き手とした場合の握り方です。

三角形だけではない。形の豊富さもおにぎりの魅力
いかがでしたか。おにぎりの形は、単なる見た目だけの違いではありません。
形を変えることで、ご飯と具材のバランス、握りやすさ、食べやすさ、そして見た目も変化します。
三角形、丸形、俵形、太鼓形…それぞれに個性があり、魅力があります。

ぜひ、色々な形のおにぎりを作ってみましょう。いつもの具材で、いつもと違う形に握ってみる。それだけで、新しい発見があるかもしれません。
そして、おにぎりを握るときには、ぜひ「どんな形にしようかな?」と想像力を膨らませてみてください。形を変えることで、おにぎり作りがもっと楽しくなりますよ。