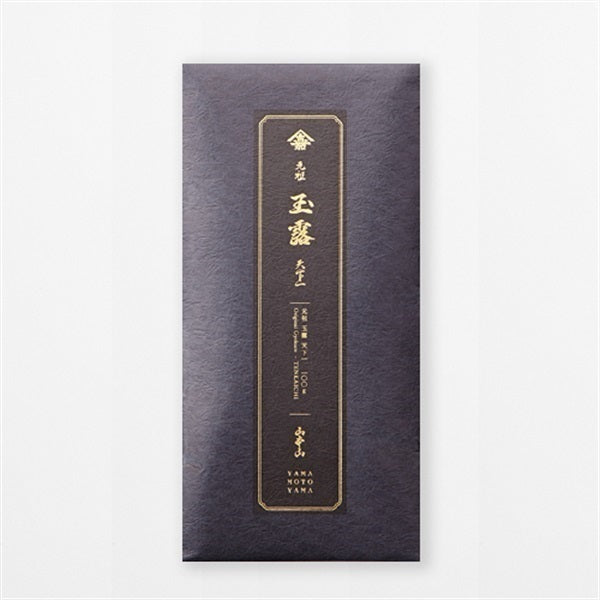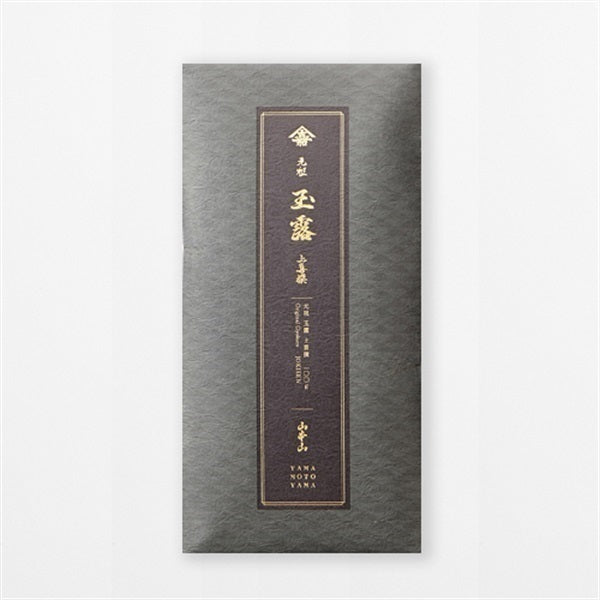緑茶を飲みすぎるとどうなる?飲み過ぎによる悪影響と1日の適量、おすすめの飲み方
はじめに
「ほっと一息つきたい時に」「食事と一緒に」「お客様のおもてなしに」・・・
日本人にとって、緑茶は生活に深く根付いた、なくてはならない飲み物の一つと言えるでしょう。
現代の忙しい生活の中で、緑茶は、私たちにとって身近な存在となっています。
手軽に購入できるペットボトルの緑茶を、毎日のように飲んでいる方も多いのではないでしょうか?
健康志向の高まりとともに、改めて緑茶の健康効果が見直されていることも、その理由の一つかもしれません。
昔ながらの急須で淹れる機会は少なくなったかもしれませんが、緑茶は様々な形で私たちの生活に溶け込んでいると言えるでしょう。

確かに、緑茶にはカテキンやテアニンなど、健康に良い成分が豊富に含まれています。
しかし、どんなに体に良いものでも、摂りすぎは禁物です。
「良薬口に苦し」ということわざがあるように、良いものであっても、過剰に摂取すれば体に悪影響を及ぼす可能性があります。緑茶も例外ではありません。
今回は、緑茶を飲みすぎることで何が起きるのか、そのリスクについて詳しく解説していきます。
同時に、緑茶の健康効果を最大限に活かすための、適切な摂取量についてもご紹介します。

緑茶の主な成分と驚くべき健康効果
古くから親しまれてきた緑茶ですが、近年ではその健康効果に注目が集まっています。
緑茶に含まれる主な成分としては、カテキン、カフェイン、テアニンなどが挙げられます。

1. カテキン
カテキンはポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用を持つことで知られています。
抗酸化作用は、体内の活性酸素を除去し、細胞の老化や損傷を防ぐ効果が期待できます。
また、カテキンには抗菌・抗ウイルス作用による感染症予防効果や血圧上昇抑制、コレステロール値低下などの効果も報告されています。

2. カフェイン
一方のカフェインは、中枢神経系を興奮させる作用があり、眠気覚ましや集中力向上に効果があります。
また、運動パフォーマンスを上げる効果や脂肪燃焼を促進する効果も期待できるため、ダイエットにも役立つと考えられています。

3. テアニン
アミノ酸の一種であるテアニンは脳内のα波を増加させることで、リラックス効果をもたらすと考えられています。
自律神経を整える効果が期待できるほか、睡眠の質向上にも役立つと言われてされており、近年はサプリメントにも多く配合されています。
またテアニンを摂取することで、手足の末梢血管が拡張され、血流が改善されるという結果が出ています。
お茶を飲むとほっとしたり、手足がぽかぽかするのは、このテアニンのおかげによるものです。
これらの成分の相乗効果により、緑茶は様々な健康効果をもたらしてくれると考えられています。

緑茶の飲みすぎによる健康リスク
しかし、どんなに体に良いものでも、摂りすぎは禁物です。緑茶も例外ではありません。
緑茶を飲みすぎることで、以下のような健康リスクが考えられます。

1. カフェインの過剰摂取
緑茶にはカフェインが含まれています。
カフェインは適量であれば、眠気覚ましや集中力向上に効果がありますが、過剰に摂取すると、不眠、動悸、めまい、不安、胃腸障害などの症状を引き起こす可能性があります。
特に、妊娠中や授乳中の女性、カフェインに敏感な人は、摂取量に注意が必要です。
日本においては、カフェインの一日の摂取量目安が明確に定められていませんが、他の国々では、健康な成人であれば1日に400mgまでが目安とされています。
以下の表を参考に、摂取量に問題がないかご確認ください。
参考:日本茶をはじめとする飲み物に含まれるカフェイン量 (100mlあたり)
| 玉露 | 160mg |
| 抹茶 | 60mg |
| コーヒー | 60mg |
| ホットココア | 35mg |
| 紅茶 | 30mg |
| 烏龍茶 | 20mg |
| 普通煎茶 | 20mg |
| ほうじ茶 | 20mg |
| 番茶 | 10mg |
| 玄米茶 | 10mg |
| 釜炒り茶 | 10mg |
| 麦茶 | 0mg |

2. 肝機能への悪影響の可能性
緑茶に含まれるカテキンは、一般的に安全とされていますが、過剰に摂取すると肝臓に負担をかける可能性があるという報告があります。
特に、サプリメントなどで高濃度のカテキンを摂取する場合は、注意が必要です。一部の人に肝機能障害などの健康被害が生じたという報告もあります。
これは、カテキンが肝臓で代謝される際に、一部が毒性を持つ物質に変化することが原因と考えられています。

これらの報告を受け、欧州食品安全機関(EFSA)は2018年、1日あたり800mg以上のエピガロカテキンガレート(EGCG)をサプリメントから摂取すると、肝臓への負担が懸念されるという見解を発表しました。
エピガロカテキンガレート(EGCG)は、カテキンの中でも特に活性が高い成分です。
とはいえ、通常の緑茶に含まれるカテキンの量では、肝臓への影響はほとんどないと考えられています。
日本人は古くから緑茶を日常的に飲んできましたが、緑茶の摂取による健康被害はほとんど報告されていません。
適量を守って緑茶を飲む場合、健康な人であれば、特に問題はないと考えられています。

3. 鉄分吸収の妨げ
緑茶に含まれるタンニンは、鉄分の吸収を阻害する可能性があります。
そのため、食事中に濃い緑茶を飲むと、飲まないときに比べて鉄分の吸収率が低下する、という可能性は否定できません。
特に、「非ヘム鉄」と呼ばれる植物性食品に含まれる鉄分は、タンニンの影響を受けやすいと言われています。
しかし、鉄の吸収には、他にも様々な要因が関わっています。
例えば、食事と一緒に摂るビタミンCは、鉄の吸収を促進する働きがあります。また、肉類に含まれる「ヘム鉄」は、植物性の非ヘム鉄に比べて吸収率が高いことが知られています。
基本的には、緑茶を飲んでも、バランスの取れた食事をしていれば、鉄分が不足することはあまり考えられません。
ただし、極端に偏った食生活を送っていたり、生理や妊娠などで鉄の需要が高まっている場合は、注意が必要です。

緑茶の1日の適正摂取量
では、緑茶は1日にどれくらい飲めば良いのでしょうか?
1日の適正摂取量は、個人の体質や健康状態によって異なりますが、一般的には5~10杯程度と言われています。
先述したように、肝機能や鉄分の吸収に影響を与えかねないカテキンについては、それほど気にかける必要はありません。通常の緑茶の摂取量であれば、影響はほとんどないと考えられています。

ここで注意すべきは、緑茶に含まれるカフェインです。
カフェイン量は、種類や淹れ方によって大きく異なりますが、普通煎茶の場合は湯呑み茶碗1杯(150ml)あたり30mg程度が一般的です。
つまり、1日に13杯程度の緑茶を飲めば、カフェイン摂取量の上限、400mgに達します。
一般的に考えて、ここまで大量の緑茶を飲むことは少ないと思うのですが、1日多くとも5-6杯までに収めると安心です。
もちろん個人の体質や健康状態によって、適量には個人差があります。また、熱湯を使用することや、長時間侵出することでカフェイン含有量も高まります。
カフェインに敏感な人や、持病がある人は、医師に相談するなどして、自分に合った摂取量を見つけるようにしましょう。
また、緑茶の飲み方にも注意が必要です。空腹時に濃い緑茶を飲むと、胃腸に負担がかかる可能性があります。食後や、薄めに淹れた緑茶を飲むように心がけましょう。

日常生活の中での取り入れ方
緑茶は、毎日の食事のお供として楽しむだけでなく、暮らしの様々なシーンに寄り添ってくれる飲み物です。
例えば、熱いお湯で淹れたカフェイン豊富な緑茶は、朝の目覚めを促す一杯に最適です。

お昼過ぎに疲れを感じたときや、集中力が途切れたと感じた時には、70℃程度の熱すぎないお湯で淹れた緑茶を味わってみてください。
テアニンとカフェインがバランスよく抽出されることで、リラックス効果もあり、再び集中力を高めるのに役立ちます。
また、食後に口の中をさっぱりとさせたい時や、脂っこい食事の後には、熱いお湯で淹れた緑茶もおすすめです。
85℃以上の熱湯で抽出することで、食中毒予防効果や虫歯予防効果のある、カテキンの一種であるエピガロカテキンガレートが豊富に抽出されます。

一日の終わりには、60℃程度の低温で抽出した緑茶が良いでしょう。
豊富に含まれるテアニンが脳内でα波の発生を促すことで、長い一日をリラックスした状態で終えることができるはずです。
血流が改善することから手足も温まり、寝つきもよくなるほか、睡眠の質改善効果もあるとされています。

まとめ
いかがでしたか。このように、緑茶は、私たちの心身を健康に導いてくれる素晴らしい飲み物です。
しかし、その恩恵を十分に受けるためには、適量を守り、適切な飲み方をすることが大切です。
「過ぎたるは猶及ばざるが如し」
この言葉の通り、どんなに良いものでも、過剰摂取は体に悪影響を及ぼす可能性があります。緑茶の力を正しく理解し、上手に生活に取り入れていきましょう。