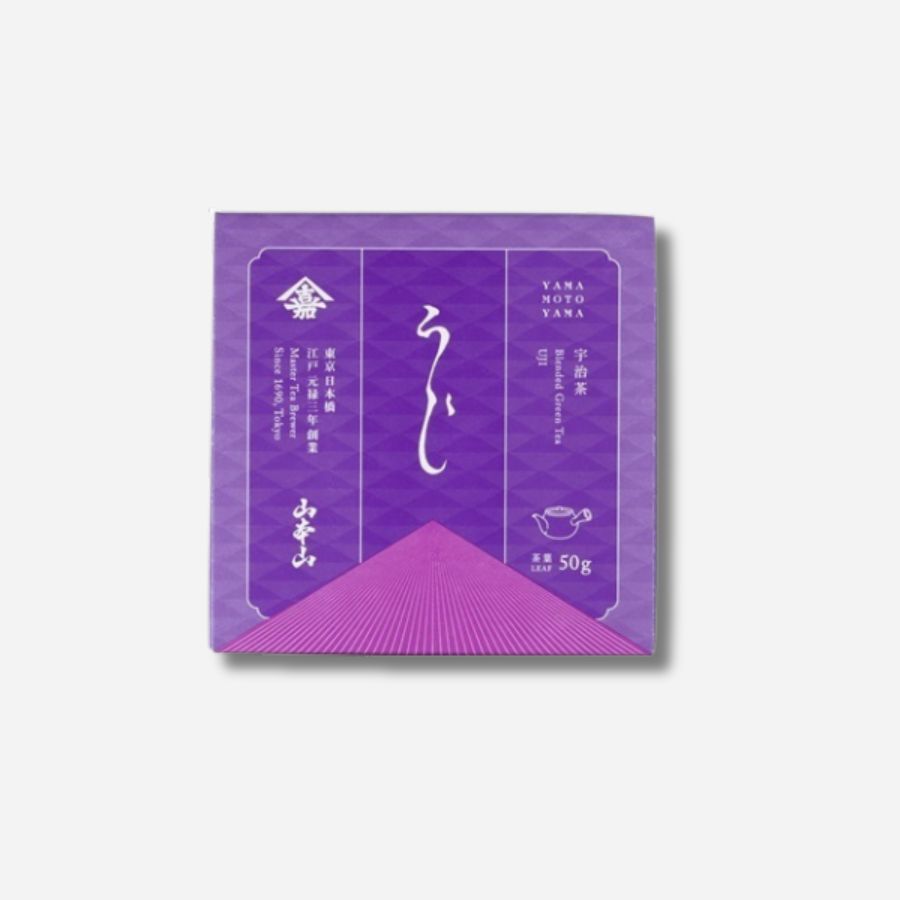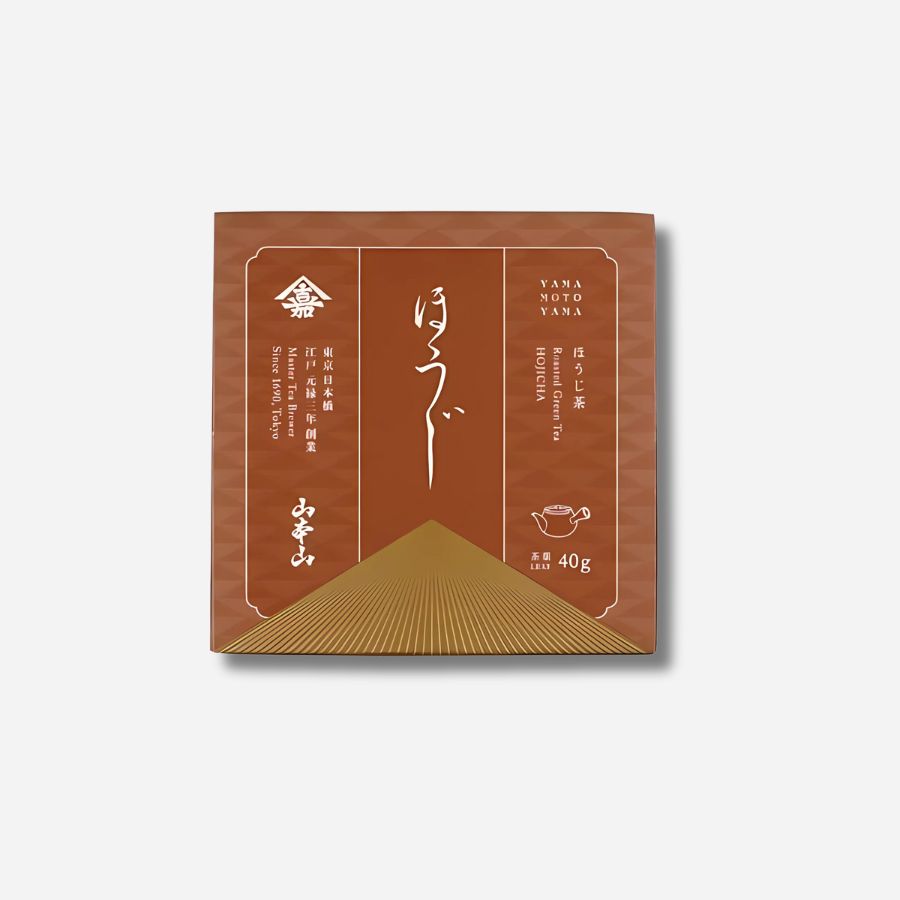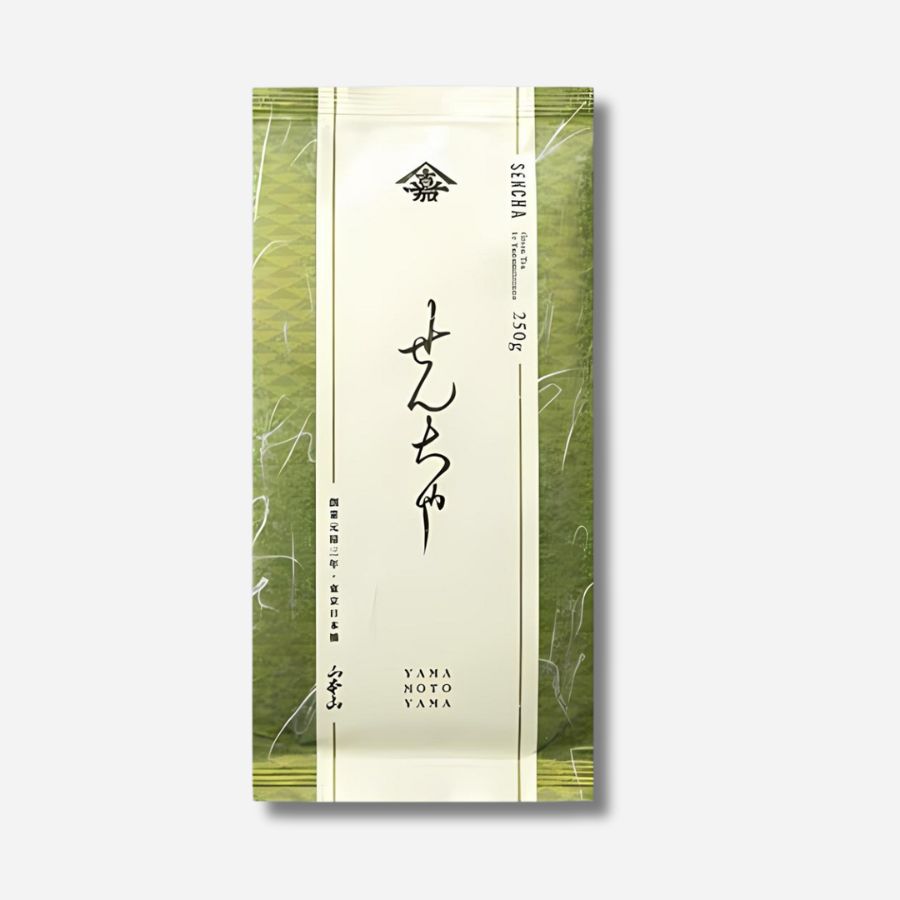【お茶の豆知識】ことわざ&慣用句で読み解く日本文化
- はじめに
- お茶にまつわることわざ・慣用句
- 無茶苦茶
- 茶柱が立つ
- 茶腹も一時
- へそで茶を沸かす
- 茶化す
- 朝茶に別れるな
- 朝茶は七里に帰っても飲め
- 朝茶はその日の難逃れ
- 朝茶には福が増す
- 濃い茶、目の毒、気の薬
- 良い茶の飲み置き
- 茶禅一味
- 茶は水が栓
- 宵越しの茶は飲むな
- 喫茶去(きっさこ)
- 且座喫茶(しゃざきっさ)
- お茶の子さいさい
- お茶を濁す
- お茶を挽く
- 袖引きたばこに押し付け茶
- 日常茶飯事
- 親の甘茶が毒になる
- 沢庵の重石に茶袋
- 酒は酒屋に、茶は茶屋に
- 茶碗を投げたら綿で抱えよ
- 余り茶を飲めば年が寄る
- 鬼も十八、番茶も出花
- 屋根ふきの茶飲み
- 粗茶
- 着物は長持ちから、茶は缶子から
- 猫も茶を飲む
- 茶の花香より気の花香
- 朝茶の塩
- 余り茶に福あり
- 色男は茶漬け飯
- うどんを茶で食う
- 茶々を入れる
- 茶碗と茶碗
- さいごに
はじめに
日本人は古くからお茶を親しみ、その文化は私たちの生活に深く根付いています。
そんなお茶には、「お茶の子さいさい」「へそで茶を沸かす」など、さまざまな言葉やことわざが存在するのをご存知ですか?
今回はそんなお茶にまつわる言葉を紹介します。

お茶にまつわることわざ・慣用句
1. 無茶苦茶
「無茶苦茶」とは、秩序や道理などが常識からひどく離れていたり、統一が取れていないこと。
お茶は正しい飲み方をすれば味わい深いものだが、この順序を誤るとただ苦いお茶になる。すなわち、お茶を台無しにして苦くすることから、無茶苦茶となる。
2. 茶柱が立つ
「茶柱」とは茶碗の中で、お茶の茎や葉軸が垂直に立っていることをいう。非常に珍しい現象であることから、茶柱が立つと縁起が良いとされ、人に話さずにそっと懐にしまうといいことがあるといわれる。
ただし、現代の精密に選別されたお茶と、注ぎ口に網の張られた急須では、茎が茶碗に出る可能性はほとんどないため、茶柱も過去のものとなっている。
3. 茶腹も一時
「茶腹も一時」とは、お茶を飲むだけでも一時的に空腹をしのげることから、わずかなものでも一時しのぎになることをいう
4. へそで茶を沸かす
「へそで茶を沸かす」とは、笑わずにはいられないほどおかしいこと。ばかばかしいことをさす。
5. 茶化す
「茶化す」とは、まじめな話を冗談などでごまかしたり、からかったりしてしまうという意味。「休憩する」という意味の「お茶にする」から派生して、「はぐらかして相手にしない」という意味が生まれた。
6. 朝茶に別れるな
「朝茶に別れるな」とは、お茶は体に良い効能があるので、毎朝でも飲んだほうが健康的であるという考え
7. 朝茶は七里に帰っても飲め
「朝茶は七里に帰っても飲め」とは、朝のお茶は災難除けといわれることや、身体にも良いから面倒に思わず飲むほうが良い、たとえ七里の道を帰ってでも必ず飲むべきという意味。
8. 朝茶はその日の難逃れ
昔から朝にお茶を飲むと、その日一日良いことがあるといわれている。また、朝のお茶は体に良いのだから面倒と思わずにその習慣を止めてはいけないという意味でもある。
9. 朝茶には福が増す
昔から朝茶は良いものとされており、朝にお茶を飲めばその日良いことがあるといわれた。「朝茶はその日の難逃れ」と同じ意味。
10. 濃い茶、目の毒、気の薬
「濃い茶、目の毒、気の薬」とは、濃いお茶は眠気が飛んで眠れなくなるが、同時に気持ちはすっきりするという意味
11. 良い茶の飲み置き
「良い茶の飲み置き」とは、良いお茶の味は後まで口に残ることから、惜しまれずに何でも使うほうが良いという教え
12. 茶禅一味
「茶禅一味」とは、もてなしの心が茶道と禅の極意という意味の言葉。「一期一会」「和敬静寂」とともに、茶の湯の精神を表す言葉として知られている
13. 茶は水が栓
「茶は水が栓」とは、お茶は水によって美味しさが変わるから、良い水を選ぶことが大切という意味
14. 宵越しの茶は飲むな
宵越しとは一晩たつこと。「宵越しの茶は飲むな」とは、一晩たったお茶は美味しくないので、お茶はいれたてで美味しいうちに飲めという意味。また、茶殻は酸化・腐敗しやすいため、一晩たったもので淹れては、健康にもよくないという教えでもある。
15. 喫茶去(きっさこ)
「喫茶去(きっさこ)」とは、本来は禅語で「目を覚まして出直してこい」という叱咤の言葉だったが、現在は「お茶でも召し上がっていきませなんか?」「お茶でもどうぞ」という意味にも解釈されており、もてなしの心を表すためによく寺や茶室に掲げられている。
類似語に「且座喫茶」という言葉があり、こちらは「しばらく座ってお茶でも飲んでいきなさい」という意味。
16. 且座喫茶(しゃざきっさ)
「座喫茶(しゃざきっさ)」とは、前項で紹介したように、「ちょっと座ってお茶でもいかがですか?」という意味のお茶の言葉
17. お茶の子さいさい
「お茶の子さいさい」とは、お手軽で簡単なこと。「お茶の子」とはお茶に添えて出される軽いお菓子のことで、お腹に溜まらないで手軽に食べられることから、簡単に片づけられる物事のことをさす。「さいさい」ははやし言葉。
18. お茶を濁す
「お茶を濁す」とは、いい加減なことで、適当にその場を取り繕ってごまかすこと。茶道に詳しくない人が濁ったお茶を淹れて抹茶に見せかけたことが由来し、いい加減な言動のことをさすようになった。
19. お茶を挽く
「お茶を挽く」とは、抹茶を石臼で挽くのは時間がある人のやる仕事であったことから、それができるほど、暇なことのたとえとして使われる。特に遊女や芸者などに客が付かない状態をいう。
20. 袖引きたばこに押し付け茶
「袖引きたばこに押し付け茶」とは、帰ろうと立ちかけた客に対して、タバコやお茶をすすめる。相手の都合を何も考えないことの例えで、行為であっても人に無理強いするのは良くないという意味。
21. 日常茶飯事
「日常茶飯事」とは、読んで字のごとく、毎日の食事のことをさす。転じて、ごくありふれたことの例えとして使われる。
22. 親の甘茶が毒になる
「親の甘茶が毒になる」とは、甘いお茶も飲みすぎると毒になることから、子供を甘やかしてばかりだと子供のためにならない、という戒めの言葉
23. 沢庵の重石に茶袋
「沢庵の重石に茶袋」とは、全く役に立たず使えないことの例え。茶袋は軽すぎて漬物石には向かないことに由来。
24. 酒は酒屋に、茶は茶屋に
「酒は酒屋に、茶は茶屋に」とは、物事にはそれぞれ専門があるので、専門知識のある人に教えてもらったほうが良いという例え。
25. 茶碗を投げたら綿で抱えよ
「茶碗を投げたら綿で抱えよ」とは、相手が茶碗を投げるほど怒ったとしても、綿でそれを受け止めるように、やんわりと受け止めるのが良い、という意味。強く出た相手には柔らかく接したほうが得策であるという教え。
26. 余り茶を飲めば年が寄る
「余り茶を飲めば年が寄る」とは、意地が汚いことを戒めたことわざ。余ったお茶を飲むのが意地が汚いことが由来
27. 鬼も十八、番茶も出花
出花とはいれたての香味の良いお茶のこと。「鬼も十八、番茶も出花」とは、安い番茶も淹れたては良い香りがして美味しいように、たとえ鬼であっても若いときはそれなりに可愛らしく、年頃になれば魅力が出てくるという意味で使われる。
28. 屋根ふきの茶飲み
「屋根ふきの茶飲み」とは、自分は何もせず人のすることばかり眺めている様子。屋根ふきは人から見えないところで休むことができるため、自分のことを棚に上げて、人のすることを眺めていることから。
29. 粗茶
「粗茶」とは、あまり上等ではないお茶のこと。来客にお茶を出すときは、上等なお茶でも「粗茶でございますが」というのが決まり事とされる。日本人ならではの「謙遜の美徳」が表された言葉といえる。
30. 着物は長持ちから、茶は缶子から
「着物は長持ちから、茶は缶子から」とは、物にはそれぞれ求め方があることを忘れてはならないという戒め
31. 猫も茶を飲む
「猫も茶を飲む」とは、生意気で身分不相応な言動を表しているたとえ。気ままに生きている猫でさえ、お茶を飲んでひと休みしたいかもしれないということから生まれた言葉。
32. 茶の花香より気の花香
「茶の花香より気の花香」とは、誠意を込めた対応の大切さを説いた教え。客人に対して香り高いお茶を出すよりも、誠意のこもった対応をすることの方が重要という意味。
33. 朝茶の塩
「朝茶の塩」とは、わずかだが欠かせないものの例え。昔はお茶に塩を入れ、泡立てて飲んでいた。今でも立て茶には塩を淹れる飲み方があり、それが転じて、このような意味となって使われている。
34. 余り茶に福あり
「余り茶に福あり」とは、残り物にはよいことがあることの例え。物を大切にすることを諭す意味もある。
35. 色男は茶漬け飯
「色男は茶漬け飯」とは、沢山の客を相手にする遊女にとっては、どんなハンサムな男性、色男であっても茶漬け飯を食う程度のことで、ありふれたものだという意味。
36. うどんを茶で食う
うどんは通常つゆで食べるのが常識。そこから、「うどんを茶で食う」とは、あえて奇抜なことをすることや、つじつまの合わないことをすることをさす。
37. 茶々を入れる
「茶々を入れる」とは、話の本筋から離れた冷やかしを入れて妨げることをいう。茶々には、妨害や無分別などの意味がある。
38. 茶碗と茶碗
「茶碗と茶碗」とは、同じ性格の人同士は傷つけあいやすいことの例え。茶碗はちょっと触れ合っただけで両方ともかけてしまうことに由来。

さいごに
お茶にまつわる言葉やことわざ、いかがでしたか?
古くから日本人に愛されてきたお茶。その歴史と文化の深さは、言葉やことわざにも色濃く反映されていますね。
日常会話の中にさりげなく使われているものから、お茶の世界ならではの専門的なものまで、実に様々。
これらの言葉を知ることで、お茶の世界がより一層広がり、深まるかもしれません。