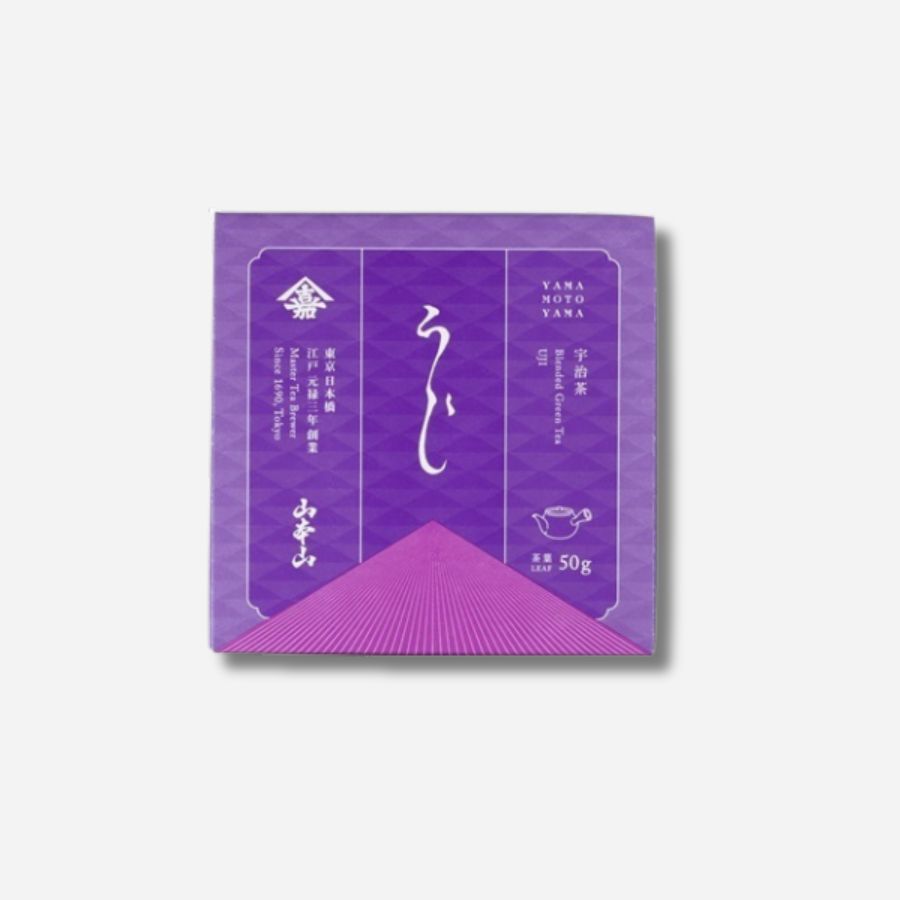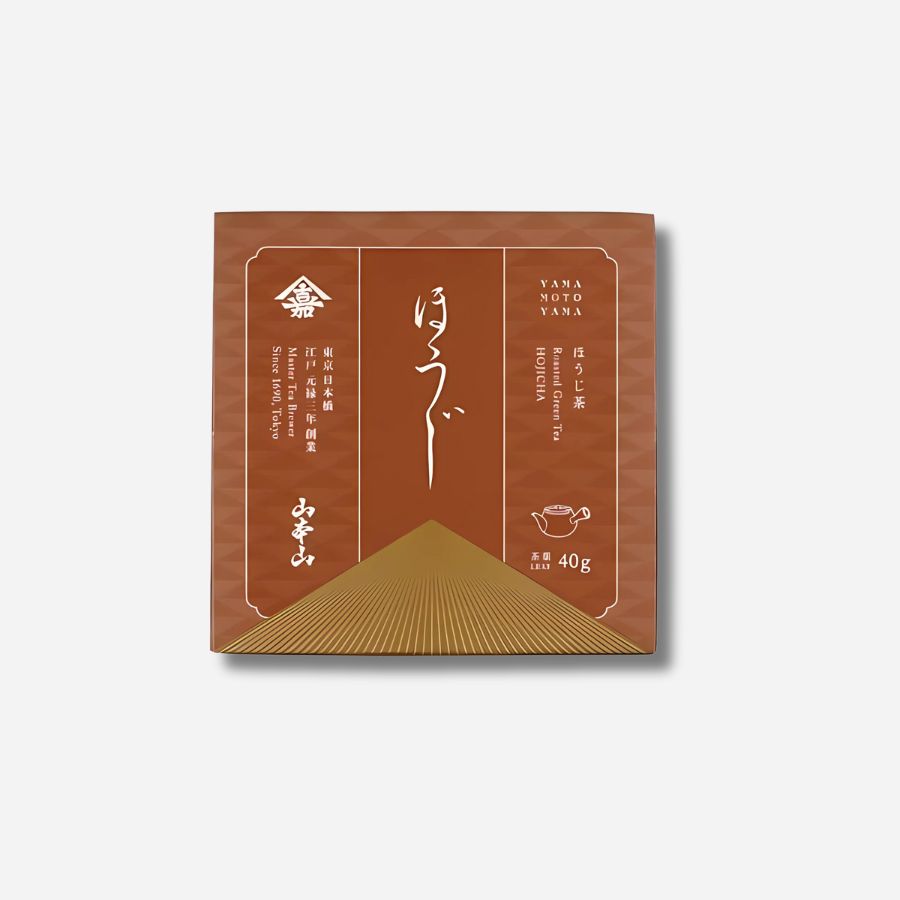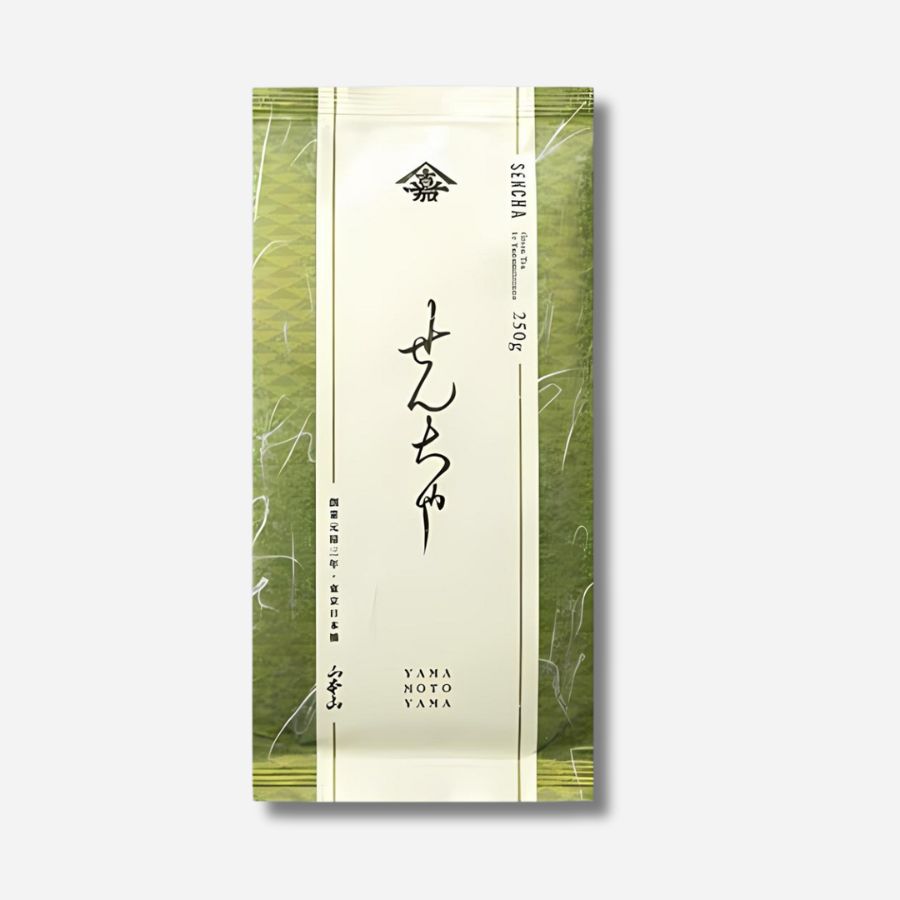じめじめ季節に要注意!緑茶で食中毒を撃退
はじめに
湿度と気温が上昇するこれからの季節は、食中毒が気になる時期です。
ところで皆さん、普段の食事中に何を飲んでいますか?
最近は、ペットボトルのお水を選ぶ方が増え、飲食店でもお茶の代わりに水だけを提供するお店が増えているようです。
しかし、食事の際の飲み物として水を選ぶ際には、特に硬水の場合、注意が必要です。

一般的に市販されているミネラルウォーターには、カルシウムなどのミネラル分が豊富に含まれています。
これらは体に必要ですが、食事中に多量に摂取すると、胃の中で胃酸と結合し、胃酸を薄めて消化酵素の働きを妨げる可能性があります。
これにより、食べ物の消化が遅れ、胃もたれや消化不良を引き起こすこともあるのです。
腎臓に疾患を持つ方にとっては、ミネラルの摂取量調整が必要な場合もあります。

緑茶の秘めたる力:食の安全と健康を守るカテキン
一方、緑茶には、私たちが思っている以上に、食事の安全と健康に役立つ素晴らしい力が秘められています。
特に、その食中毒予防効果は注目に値します。
この効果は主に、緑茶に豊富に含まれるカテキンの働きによるものです。
カテキンは、緑茶の渋みの元となるポリフェノールの一種で、強力な抗菌作用を持つことが科学的に証明されています。

食中毒を引き起こす細菌やウイルスが体内に侵入すると、これらは細胞内で増殖し病原性を発揮します。
緑茶に含まれるカテキンは、これらの病原体に対し、細胞膜を損傷させたり、増殖に必要な酵素の働きを阻害したりするメカニズムにより、その増殖を抑制する作用を持つことが確認されています。

食中毒の原因となる菌は、体内で増殖して症状を引き起こす腸炎ビブリオやウェルシュ菌のような「感染型」と、食品中で毒素を作り出すブドウ球菌やボツリヌス菌のような「毒素型」に大きく分けられます。
数々の研究で、緑茶に含まれるカテキンがこれら両方のタイプの原因菌に対して効果があることが実証されています。

例えば、原征彦氏らの研究では、緑茶に含まれるカテキンが、一般的なお茶の半分ほどの薄い濃度でも、これら食中毒菌に対し強い増殖抑制効果があることが示されました。
さらに、毎年猛威を振るう腸管出血性大腸菌O-157に対しても、通常のお茶のわずか4分の1程度の低濃度で殺菌効果があったと報告されています。
加えて、抗生物質が効きにくいことで知られる黄色ブドウ球菌に対しても、カテキンが低濃度で殺菌効果を発揮することが証明されています。
このように、緑茶に含まれるカテキンは、多様な病原菌に対して抗菌作用を発揮することで、食中毒のリスクを低減する有効な手段となり得るのです。

伝統と科学の融合:食事のパートナーとしての緑茶
古くから「お寿司とお茶」がセットで当たり前のように親しまれてきたのは、単なる習慣ではありません。
冷蔵技術が未発達だった時代、生魚を扱う寿司は食中毒のリスクが高かったため、殺菌効果のあるお茶を一緒に飲むことで、食の安全を確保しようとする先人たちの知恵が働いていたと考えられています。
同じように、食中毒が増えやすい夏場に食事とお茶を組み合わせる習慣が定着したのも、理にかなったことだったのです。

緑茶は、食中毒予防に役立つだけでなく、消化を助けたり、口の中をさっぱりさせたり、口臭予防にも繋がったりと、様々な健康効果が期待できます。
これからの季節、食中毒のリスクが増す時期には、ぜひ食事の際にはお水の代わりに緑茶を飲む習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか。
美味しいだけでなく、私たちの食の安全と健康をしっかり守ってくれる頼もしい一杯となるはずです。